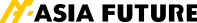マスメディアが捉えるツイッターとは? あまりに時代遅れ
| 3月6日付 よみうり寸評[2010.03.06] なぜ、こんなものが流行るのか。インターネットの世界で利用者が急速に増えている 「ツイッター」にそう首を傾げている人は多かろう。140字以内の短文を誰でもネットに発信できる。読んでもらう相手を決めておく必要はない。 いわば「つぶやき」だ。「腹減った」「もう寝る」もある。 政治経済や国際情勢、宇宙を語っている人もいる。最近は政治家もよく「つぶやく」。 このうち今週話題になったのが原口総務相だ。1週間前のチリ地震で自ら津波情報をつぶやいて発信。 「ツイッター」は英語で「鳥のさえずり」。人々があちこちでつぶやく様を指すらしい。 政治家の情報発信には格好の道具だ。ただ発言を取り消せない。 |
このコラムを読み、思わず笑ってしまった。
自身もツイッターユーザである読売新聞社が、どういうわけかツイッターを疑問視。毎度この手の話で思うのが、メディア内でも古いタイプの人ほど、インターネットで展開される新しい情報交流ツールやそのコミュニティに懐疑的で否定的であること。
大して利用もしていないだろうに、自分たちが作ってきた情報の常識を覆す可能性があるものに対し、ネガティブなコメントを発信するケースが多い。批判からは何も生まれません。
ビジネスとしての発展もありません。僕は、ツイッターがすごいものかどうか?は現状では正確に説明できません。しかし画期的なツールであることは間違いありません。何ができてどんな未来を創造できるのか?を考えることは重要だと捉えています。
ということもあり、今回のこんなコラムについて私なりに、意趣返しで返答してみたいと思います。
気軽につぶやいてもらっては困る? なぜ、こんなコラムを書けるのか
| インターネットの世界で利用者が急速に増えている「ツイッター」に 首を傾げたと書いた「よみうり寸評」に首を傾げた人こそ多かろう。 最近は新聞社もよく「つぶやく」。 ニュースと向き合い、日々奮闘しているYOL(ヨミウリ・オンライン)の編集記者は、 「ツイッター」は英語で「鳥のさえずり」。 つぶやき数も今週、累計100億回を超えた。 ただ一部のメディア社員が理解していない。スッパ抜かれるのが怖い。 |
お後がよろしいようでm( _ _ )m
私のツイートもよろしくお願いいたします(/・ω・)/
Tweets by matsukiyoippei