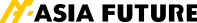実は昨年書いた論文に関し、ある人から感想と疑問点が出た。とても鋭い指摘であり、思わずしばし考え込んでしまったのだ。
簡単に言えば、私たち一人ひとりと、情報を発信・交流する媒体との相関関係の分析が今改めて必要なのでは?という意味合い。
そう、今まで僕自身もだったけど、「プッシュ」だ「プル」だとしか見ていない。つまりマス・メディアは「押し付け情報」、他方で
ネットは「引っ張り情報」だという考え。
現在規制をかけている総務省にしても、放送・通信についてその程度の認識しか持っていないだろうと思います。
それゆえに放送と通信の概念が生まれ、放送をさらに広義に捉えマス・メディアに対する数々の概念と規制が生まれているのでしょう。
そこで。
僕なりに現在において巷に広がるさまざまなメディアの相関関係図を作ってみました。
ポイントは「能動的or受動的」という概念のほかにもうひとつ「有償or無償」という意味合いを加えてマトリクスで考えている点です。
この有償or無償はゼロかイチという意味合いだけでなく、「自分がそこから情報を取るために、どの程度懐を痛めているか?」という極めて主観的な意味合いをこめています。
例を挙げるなら、同じ新聞でも「宅配」<「駅売り」で有償度が高い…ってな感じ。定期購読はなんとなく習慣で当たり前。カネを払う感覚が駅売りほど強くない。。 でも駅売りは、その記事がセンセーショナルか情報が欲しいかどうか?などで小銭を払うかどうか消費者が決めるわけでそのあたりが「主体的にゼニを払うか?」という意味合いです。
ということで、こちらをご覧ください。いかがでしょうか?この図の例で言えば…
○ラジオよりもテレビの方が「番組」で接触を変える
CMのたびに「ザッピング」が起こる …より主体的です。
○学校の講義なんかは、カネ払っているくせに受動的。
○webでもいわゆる「ポータル閲覧」は会社や学校のインフラで
行う分、結構テレビ的。他方でポータル<ブログ<SNSと能動性が高い。
○携帯コンテンツはやっぱりまだまだ「ゼニ払っている」感はあるでしょう。
(学生は親が払ってる場合はもちっと左に移動するでしょうが…笑)
とまぁこんな風に思うわけです。このような媒体の捉え方は、今後の情報戦略に役立つかもです。ご意見待ってまふm(_ _)m
ちなみに。
この件で質問をくれたのは、シリコンバレーに一緒に行った大学院生の方でした。の○たけ君 感謝m(_ _)m
業界関係者とヘビーリスナー向け ラジオ媒体の課題に迫るブログ
【ラジオ広告営業に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(1)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(2)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(3)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(4)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(5)
ラジオ業界解説|ラジオを売るということ(6) これって背任?
ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(1)
ラジオ業界解説|ラジオショッピングの効果(2)
【ラジオ媒体価値の実態に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(1) 大切な1週間
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(2) SIU(Set in Use(セット・イン・ユース))
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(3) ラジオが格下に・・・_| ̄|○
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(4) メディア接触に関する調査 4マスがさらに減少??
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(5) ラジオ媒体の効果
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(6) 聴取率調査の実態
ラジオ業界解説|ラジオ聴取率調査(7) ラジオの媒体価値は低下したのか?
【ラジオ番組の裏側・実態に関する話題】
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(1)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(2)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(3)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(4)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(5)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(6)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(7)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(8)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(9)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(10)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(11)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(12)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(13)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(14)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(15)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(16)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(17)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(18)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(19)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(20)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(21)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(22)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(23)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(24)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(25)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(26)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(27)
ラジオ業界解説|ラジオは何故面白くないのか?(28)
ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(1) ライブドアvsニッポン放送
ラジオ業界解説|番組は誰のもの?(2) ライブドアvsニッポン放送
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(1) その日 9.11
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(2) テレビ・ラジオの出演者の人件費の実態
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(3) 商店街寄席
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(4) ラジオとインターネット
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(5) 風呂とラジオ
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(6) Podcastingとの関わり方
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(7) 情報の二極化
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(8) シマのラジオ
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(9) これも吉報みたいなもの
ラジオ業界解説|番組制作の裏側(10) サス サステイニング・プログラム(Sustaining program 自主番組)
【ラジオ業界の話題】
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(1) 激変の始まり ライブドア:ニッポン放送株を取得
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(2) 分社化の蠢動
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(3) ワンセグの脅威
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(4) メディアの特徴の変容
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(5) 媒体の移り変わり ラジオ→ワンセグ?
ラジオ業界解説|ラジオ業界ニュース(6) RADIO-i(レディオ・アイ)の終了